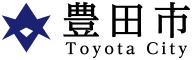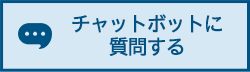2025年2月14日(金曜日)市長記者会見
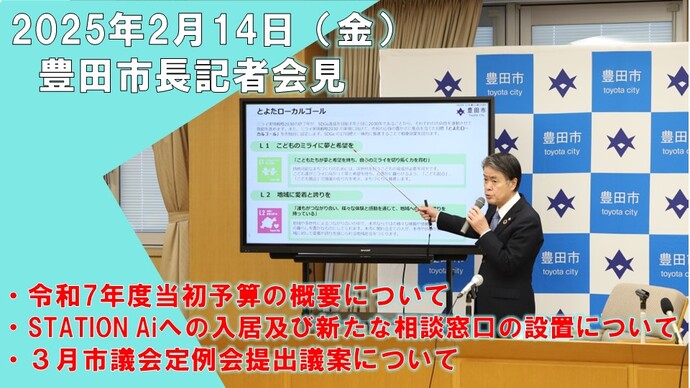
- 1 時間
- 午前11時~
- 2 場所
- 南51会議室
- 3 内容
-
- 令和7年度当初予算の概要について
- 「STATION Ai」への入居及び新たな相談窓口の設置について
(備考)市内のオープンイノベーションを推進するもの - 3月市議会定例会提出議案について
配布資料
-
令和7年度 当初予算案の概要 (PDF 2.3MB)

-
令和7年度 当初予算 施策別事業集 (PDF 1.3MB)

-
令和7年度 当初予算関連資料 (PDF 398.1KB)

-
市内のオープンイノベーションを推進 「STATION Ai」への入居及び新たな相談窓口の設置について 報道発表資料 (PDF 626.7KB)

市長説明
令和7年度の当初予算について説明させていただきます。
令和7年度の当初予算は、2025年度から始まります第9次総合計画のスタートの年となってまいります。総合計画は、長期の「ミライ構想」と当面5年間の「ミライ実現戦略2030」の2本立てで構成されています。
今回の予算は一言で言うとするなら、ミライ実現戦略を確実に実現していく「ミライ実現パワーアップ予算」という言い方になるかと思います。このような思いで令和7年度の取組を進めてまいりたいと思います。
ミライ実現戦略2030には、注力する視点が3つあり、2つの取組方針と5つの取組目標を設定しています。今回の予算はこの構成に合わせて予算を組んでいます。
もう1点、総合計画の中で、SDGsに関連してローカルゴールというものを設定しました。一般的には17のゴールがありますが、豊田市独自にローカルゴールを設定いたしました。17のゴールは国連が定めたグローバルな目標ですので、私たちが仕事をしていく上で17のゴールすべてがフィットするかというと、そういう訳ではないです。
豊田市がこれからのまちづくりをどこに注力するのか、どこに力を入れていくのかと考えた時に、SDGsの横の串刺しをしようとすると別の視点のゴールを設定した方がいいだろうという議論の中で生まれたのが、この2つのローカルゴールです。
「ローカルゴール」という呼び方は豊田市独自のものです。このようなゴールを設定している自治体はほとんどありません。
豊田市の場合は、1つは「こどものミライに夢と希望を」。これはこども目線、こども起点で考えていこうというものです。もう1つは「地域に愛着と誇りを」です。シビックプライドのような思いです。この2つをしっかり押さえることによって、色々な予算を組むときも、この2つの視点をできるだけ取り込んでいこうという考え方です。
具体的な事業について説明させていただきます。
取組目標(1)「こどもが多様な生き方・暮らし方を選択できる」についてです。これは、先ほどの2つのローカルゴールを重視した取組になっています。
将来を担う子どもの活動や体験の機会を充実させることによって、子ども起点で、そして地域に愛着や誇りをという狙いです。まず地域資源を生かした遊び、学び、体験の機会の充実ということで、とよた地域クラブ活動を推進します。
昭和の時代には、子どもは家庭でしつけ、学校で学んで地域で育つという言い方がされました。それ以後、平成に入ってそのような言い方がなくなって、今はほぼ学びも育ちも学校へというような傾向が強いのではないかと思っています。
そのことが、学校の教育現場における疲弊や働き方改革のような話題が出てきてしまう状況につながっていると思います。そこで、地域で子どもが育つ環境を、この機会を捉えてできるかどうかというのは、とても大きなことだと思っています。
部活の地域移行にしても、決して学校の多忙化解消ということだけではなくて、本来子どもが地域の中で育つことができるような地域を目指しましょうというメッセージを少し強く打ち出していきたいと考えています。
次に、快適な地域体育館の整備に向けての検討についてです。夏前には市内の全ての小中学校の体育館、武道場にはエアコンの設置が完了する見込みです。その次の段階として、市内にいくつかある地域体育館の暑さ対策を引き続き検討していくというのがこの新規の取組です。
続いて自ら考え判断する教育の推進についてです。「WE LOVEとよた教育プログラム」の整備は新規になりますが、実はそれぞれの学校で「WE LOVEとよた」という視点でのプログラムの開発はこれまでも進めてきていますので、今回新規で掲げた意図が、これまでの取組を総括して一度体系付けて新たにスタートしようという意味での新規になっています。
次は子どもが多様な人の暮らし方を選択する中での愛着、誇りの部分です。まずは、クルマのまち豊田市の特徴をどのように考えようか、あるいは博物館、美術館といったミュージアム、スポーツ施設をどう生かしていこうかというのが、資料の中の日本をけん引するモビリティ産業の振興、「クルマのまち」の顔としての魅力的な都心の形成、ミュージアムを生かしたまちづくりになります。
ラリーをいかしたまちづくりの推進では、11月6日から9日にかけてラリーを開催します。その際の私たちの重要な視点は、産業振興、山村振興、交通安全、この3点です。
取組目標(2)「誰もがつながり合いの中で安心して自分らしく暮らすことができる」についてです。
希望する誰もが安心して結婚や子育てができる環境づくりをさらに拡充するということで、これはこども・若者への主な施策一覧とも関係してきます。資料では小・中・高校生、ミライ形成期、家族形成期と一覧で今回示しています。
豊田市で生まれ育つということが一体どういう状況なのかということを一覧で見ていただきたいという思いです。どうしても事業の紹介が単発の特出しで出てきますので、そうすると、市民の皆さんにとってはよくわからないと感じています。
人生は連続性のある中で展開していきますので、その連続性のある人生を見通した時に、この豊田市で生まれ育つ、あるいは子どもを育てるというのが一体どういうことなのかということを一度ご覧いただいて、やはり住み続ける、住んでみたい、行ってみたい、そういう豊田市を感じていただきたいという意図があります。
この中で、小・中・高校生の時は先ほどのWE LOVEとよた教育プログラムに加えて、高校生バス通学者への支援を行います。これはすでに報道発表させていただいていますが、とりわけ中山間地の高校生ができるだけ自宅から通えるようにという取組です。
高卒人材と企業との就労マッチング支援では、なかなか上手くマッチングできないという現場の声がありますので、ここにも力を入れてきたいと思います。ミライ形成期になり、義務教育、高校での学びの期間を過ぎると、いよいよ次のステップに向かって自分自身のライフデザインをどう形成していこうか、というようなことに対しての取組です。あるいは、新しい生活に向けた賃貸住宅のリノベーション。住むところも重要ですので、こうしたことも含め、医療の関係も負担し、トータルで取り組みます。また、家族形成期には、一覧のようなトータルで家族形成期のご家庭を応援しますというスタンスです。
取組目標(3)「産業中枢都市として深化し続ける」についてです。戦略的な産業基盤の整備と立地支援ということで、設備投資の促進、あるいは今回新事業に着目しており、イノベーションを創出する仕組みづくりや、新たなプレイヤーの活躍促進、こういった新しい時代に向けての企業、事業者の皆さんのチャレンジを応援してまいります。
また、地域企業の人材確保に向けたマッチング機能の充実として、人材確保という意味で現場がご苦労されている点での支援です。労働需給シミュレーションをしたときに、今後ますます需要が増加するにも関わらず、供給がどんどん減少していきます。
大切なのは、色々な人材が画一的な働き方を選択するということにはこれからはならないだろうと思っています。それぞれの人材が、色々な働き方、こういう働き方ならできる、こういう働き方なら自分の能力を発揮できるというものと、企業側からの労働力の確保が画一的な雇用基準ではなくて、この人材の多様な働き方に合う働き方を提供するというようなマッチング機能を充実していく取組を始めます。
取組目標(4)「将来を展望した都市環境の形成を進める」についてです。都市と山村の良好な住環境確保に向けた取組を推進してまいります。こちらは、土地利用制度の戦略的な活用、住宅における危険木解消の推進に取り組み、現場でお困りのことについて現実的な対応をしていくという方針を持っています。
また、地域の防災力強化等に向けた取組については、特に新しいということではなくて、これまで続けてきたことをさらに浸透させる、さらに底辺を広げるということを着実に継続していく必要があると思ってます。
そして都心については、2026年9月のアジア大会が1つのポイントになってまいります。アジア大会までに、豊田市駅西口はペデストリアンデッキ・バス乗降場工事を終え、2026年の4月には供用を開始する予定です。豊田市駅駅舎についても、リニューアルオープンをアジア大会の前までに、豊田市駅東口はペデストリアンデッキの耐震補強やロータリー整備はアジア大会の前までに、一方で、アジア大会後も継続して整備がさらに進んでいきますので、都心地区の全体が落ち着くのは今しばらく時間がかかる見込みです。
取組目標(5)「脱炭素社会の実現に挑戦する」についてです。脱炭素は、今、様々な取組を進めていますが、2030年に50パーセント減らすという目標についてはなかなか厳しいとみています。厳しい中でも、できる限りの手を打っていこうということと、特にゼロカーボン、カーボンニュートラルを目指す時には、劇的な技術開発などが誕生しない限りは難しいかなというのが正直なところです。ですから、やれることをとにかくやり、併せて新たな技術開発などをしっかりウォッチして、いち早く導入していく姿勢で今後も継続していくことになろうかと思います。
水素については、どれだけの可能性があるかは、正直よくわからないんですが、水素が選択肢の1つとしては確実にあるという認識です。今回の水素関連で、これもできる範囲です。今の段階で導入できる技術、製品を豊田市としてはいち早く導入していこうと思っています。おそらく水素社会を目指す一環には違いありませんので、そういう姿勢で取組をこれからも進めていこうと思います。
続いて「市民が安心して暮らすことのできる取組」についてです。これは安心の一丁目一番地のところです。健康・福祉、交通安全・防犯は新規事業というのが出てまいりません。出てこないのは、ほぼ豊田市としては色々なメニューをすでに手がけているという認識です。
それぞれの取組をさらに深めていき、例えば交通安全・防犯でも、特殊詐欺被害防止対策の推進、これは色々なところで知恵を絞って民間の皆さんとも一緒にやっていますが、なかなか被害が収まっていかないので継続して粘り強くやっていくことだと思います。交通安全も同じです。
続いて「公共施設開館周年事業」についてです。今の段階では内容が固まっていないのですが、令和7年度はかなり施設の周年事業が重なってまいります。例えば、鞍ケ池公園は60周年、市民文化会館は50周年、美術館が30周年です。この周年を捉えて、記念になるようなものをやっていこうと話をしています。
ただ、今の段階では具体的に申し上げるものがありませんので、その都度情報提供させていただきますので、取材をしていただけたらと思います。
今まで申し上げたような取組を積み重ねて、予算規模は2,197億円で過去最高額です。
歳入の特徴<市税>は、法人市民税が当初予算比50億の減ですが、豊田市の法人市民税は年度でかなり増減しますので、これは通常の範囲だと思っています。個人市民税、固定資産税が安定的に増加していますので、とてもありがたいと思います。
歳入の特徴<市税以外の歳入>です。国県支出金は歳出の事業によって大きくぶれてまいりますので、令和7年度は大規模の歳出事業は国県支出金の対象となる事業が多く、その分増額になっています。
歳入の特徴<市債(借入金)>のうち、市債残高は平成28年からの記載になってますが、私が市長に就任したのが平成24年の2月です。平成24年度の当初予算の市債残高は930億円でしたが、3期プラス1年で364億円になっており、それだけ借金の額を減らしたということです。この削減額は566億円になります。
歳入の特徴<基金(繰入金)>です。基金は令和7年度は876億円で、平成24年度当初予算では343億円でした。その差が533億円です。
借金を566億円減らして、貯金を逆に533億円増やしたという状況です。これを足すと1,099億円になります。色々な財政状況が想定される時に、税収が落ち込んだ時には市債の借り増しする、あるいは基金の取り崩し金を増やす。安定した時には基金に積む、市債の借り入れを抑制するということをやっていきますので、平成24年当時と比べて1,000億円ぐらいの余力ができていると評価することもできると思います。
歳出の特徴<義務的経費>です。義務的経費というのは、支出せざるを得ない、調整が効きにくい項目ですが、一般的に人件費、扶助費、公債費を指しています。この中で公債費、要は借入金をどんどん減らしてきていますので、償還額が割と安定して推移しており、これは非常に強みだと思います。一方で、扶助費が社会福祉、教育、色々なことがありますので増額になってます。人件費についても、色々な制度が変わってきてますので、増加要因が出てきています。義務的経費の動きは丁寧に見ていく必要があると思っています。
歳出の特徴<その他経費>です。普通建設事業費が年度によって大きく増減します。令和7年度は大規模事業が重なってますので、令和6年度と比べてかなりの増額になっています。補助費等は、最近の物価高騰対応の給付費の増に加え、後期高齢者療養給付費負担金、私立認定こども園運営補助は経常的に発生していきますので、補助費等の増額というのはしっかり見ていかなければいけないと思います。物件費のうち、今回の小・中・特別支援学校タブレット更新で34億増ですが、年度によってこうしたものが変わってくるということを冷静に見ていく必要があると思っています。普通建設事業費は、先ほど触れましたけれども、増額要因がたくさんあります。財政規律を守るという意味では、市債や基金はしっかりその仕組みを生かしていかなければいけないと思いますし、そのことによって財政規律をしっかりと守っていきます。
一方で、投資すべきものは積極的に投資をしていくと、そのメリハリをしっかりつけていく必要があると思っています。
更なる歳入確保、事業・事務の最適化等の推進です。今回の予算編成にあたりましても、積極的な歳入確保ということで38.3億円、事業、事務の最適化等の推進でマイナスの14.9億円、合計で53億円程度の効果を生み出していると評価しています。
当初予算については以上です。
続いて、『市内のオープンイノベーションを推進 「STATION Ai」への入居及び新たな相談窓口の設置について』説明申し上げます。
豊田市は、これまで、ものづくり創造拠点SENTANの市内ものづくり企業等の新事業展開への支援や豊田市つながる社会実証推進協議会のプラットフォームを活用した先進実証などを誘致・実行することで、地域経済の活性化や先進技術による地域課題の解決に向けた取組を推進してまいりました。
これらの取組の活性化や、スタートアップ企業等と市内企業とのオープンイノベーションの推進を図るため、このたび、国内最大級のオープンイノベーション拠点であります「STATION Ai」内に、本市の新事業展開の支援や先進実証を担当する職員等が活動できるスペースを設けて、同施設で活動するスタートアップ企業等との連携強化を図ってまいります。
また、併せて新事業創出を志す人たちの起業から実証、社会実装までの流れを一元的かつ円滑に支援できるよう、新たな相談窓口「はじめるとよた」を設置します。
具体的な取組概要を説明申し上げます。
「STATION Ai」への入居日は、令和7年2月18日(火曜日)です。この日を皮切りに、同施設オフィスフロア内の固定席を拠点として、本市の新事業展開への支援や先進実証支援に実績のある職員等が駐在し、本市の支援策の紹介や、同施設内で活動する様々な企業と市内企業のつなぎ役を担ってまいります。
新たに設置する相談窓口「はじめるとよた」では、本市で起業や事業活動、先進実証を行いたいスタートアップ企業等を対象に起業に関する相談や市内企業とのマッチングに関する相談・調整、先進実証に関する相談対応を行ってまいります。
本市のスタートアップ・実証相談先として、これまでの「ものづくり創造拠点SENTAN」、「豊田市つながる社会実証推進協議会」に「STATION Ai」を加え、起業や先進実証等の相談先を「はじめるとよた」と銘打って企業のニーズに合った支援策を迅速に提供してまいります。本市では、「STATION Ai」への入居を契機として、これまで取り組んできたオープンイノベーションを加速し、我が国を代表する産業中枢都市として、新たな産業の創出につなげてまいります。
また、入居を記念して、スタートアップ企業等へ本市のこれまでのスタートアップ支援や実証支援について紹介するイベントを開催する予定です。3月13日(木曜日)の午後6時30分からです。場所は「STATION Ai」の1階にありますイベントスペースです。
今考えていますのは、本市がこれまで支援してきた企業2社、空飛ぶクルマを開発している株式会社SkyDrive、1人乗りのEVを開発しているLean Mobility株式会社に登壇していただいて、豊田市がどういう関わりをこれまで持ってきたのか、あるいはこの2社がどういう期待を持っているのか、というようなことについて発表する場を設けたいと思っています。
私からは以上です。
PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問合せ
市長公室 広報課
業務内容:広報とよた、報道対応、CATV市政番組、ラジオ市政番組、市政記録映像、市ホームページ管理運営などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)![]()
電話番号:0565-34-6604 ファクス番号:0565-34-1528
お問合せは専用フォームをご利用ください。