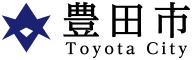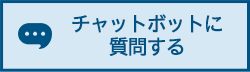広報とよた2025年2月号 特集 美しい、小原の和紙。

豊田小原和紙(以下、小原和紙)は、伝統的な技法で一枚一枚丁寧に作られています。
その紙漉きの技術は、室町時代に伝えられたといわれ、小原和紙工芸という美術工芸として現在も大切に受け継がれています。
今号の特集では、次代へと受け継がれながら、自然の質感を生かし、 独自の美を創り出す小原和紙の魅力に迫ります。
様々な表現方法で
近年、様々な創作に用いられ、ますます広がりを見せている小原和紙。 絵画はもちろん装飾品や雑貨など、和紙ならではの繊細な美しさと温もりを活かした作品が展開されています。




左「ハイブリッドいのしし」中「ウマノカブ」右「招き猫と五平餅」
小原和紙の魅力を語る
小原和紙工芸や伝統的な手漉き技法。その技術は、作り手の手から手へ大切に受け継がれながら、進化を続けています。小原和紙に魅了され、革新的な作品を作るお二人にお話を伺いました。
小原和紙工房 蓬莱館
加藤 英治さん
小原和紙工芸の新しい技術向上と表現方法を模索しながら、アート作品やインテリアの創作活動に励む。
唯一無二の価値を提供したい
小原に生まれ、幼い頃から和紙に親しんできました。高校進学後はしばらく和紙から離れていましたが、大学在学中の帰省時に、たまたまご縁があって山内一生先生の工房をお手伝いさせていただくことになりました。「和紙づくりが好き」という当時の気持ちを思い出しました。それがこの世界に入るきっかけでしたね。
和紙の魅力は、光の当たり方によって表情を変えるところだと感じています。その魅力を活かした、人々にとって何か価値のあるものを提供できないかと創作活動を続けてきました。色々と模索しながら、ランプシェードや屏風など生活の身近にあるものに行きつきました。大量生産ではない唯一無二のものとして、デザインには細かくこだわっています。
自分の作品を通して、小原和紙の認知度を広めるため、数年前から異業種交流会に参加し、様々な業界の人たちと意見交換をする機会を大切にしています。昔は、作家自身が宣伝することはほとんどなかったんですけどね。そこで出会った人たちと仕事をさせていただくこともあり、美術工芸作品としての小原和紙の繊細で美しい魅力が、多くの人の目に触れる機会をこれからどんどん増やしていけたらと考えています。

小原和紙のふるさと 和紙工芸体験館
難波 沙帆さん
市内小・中学校(一部を除く)と特別支援学校の卒業証書の紙漉きや自身の創作活動に励む。
紙漉きは、結果が目に見えて分かるのが楽しい
小原和紙との出会いは、和紙工芸体験館での紙漉き体験でした。デザイン科の高校に通っていたこともあり、授業で紙に触れることが多く、次第に和紙にも興味を持つようになりました。
実際に体験してみると、他の産地にはない独特の技法や絵漉きが面白くて。高校卒業後に和紙工芸体験館の職に就くことにしました。
主な業務は、卒業証書用の紙を漉くことです。業務に就くまでには、この地域の伝統的な手漉き技法を習得することが必須で、先輩に認めてもらうまでに半年かかりました。
1日に40枚程紙を漉いていますが、一枚一枚同じ厚さに仕上げなければいけないところが難しいです。作業工程は同じでも、材料の状態や気温などにより毎回違う動きが求められます。漉いた紙には作り手の気持ちが質感となって現れるので、そこが面白いなと感じています。
紙漉きを始めて5年目になります。目指す道のりはまだまだ長いですが、先輩方の漉き方を見て、これからも学び続けていきます。
また、ここ数年は創作活動にも力を入れています。作品のテーマは、小原の自然からインスピレーションを受けることが多いです。小原和紙に魅了されて小原に移住し、このまちのことをとても気に入っています。
今後も様々なことに挑戦し、小原和紙のこれからを担っていきたいです。

令和6年度豊田市美術展の工芸の部で市長賞を受賞。
小原和紙を知る
1 歴史
小原和紙のはじまりは、室町時代にまで遡ると言われています。昭和初期までは、三河森下紙(みかわもりしたがみ)という番傘に用いる紙を生産していましたが、その後生活様式の変化などに伴い、需要は減少していきました。
そのような中、工芸家の藤井達吉が小原和紙の質の良さに着目し、小原の紙漉きたちに草木や土を使って和紙に色を付けることを指導しました。さらに、染色した和紙原料を漉き込んで絵を描くことを考案し、藤井に師事した山内一生氏らによって小原和紙工芸として発展していきました。現在は、額絵、屏風などのほか、現代の生活にも溶け込むランプシェードや壁紙などが制作されています。
2 伝統的な工法
〔原料の処理〕
12月から1月にかけて、和紙の原料となる「コウゾ」を刈り取ります。大きな釜で蒸したら、温かいうちに樹皮をはぎ取り、付着している黒皮をそぎ落として白皮にします。
〔原料の加工〕
白皮を柔らかくなるまでアルカリ液で煮ます。水で洗ってアク抜きをし、白皮のキズやゴミを丹念に取り除いたら、繊維が綿のように細かくなるまで叩きます。
〔紙漉き〕
舟(水槽)の中で繊維と水、粘液を混ぜます。簀桁という専用の道具を前後左右に揺らし、和紙を漉きます。漉いた和紙を重ね、水を絞り天日干しで乾燥させたら和紙の完成です。
3 継承に向けた取組
小原和紙のふるさとでは、小原和紙を後世へ伝えることを目的に、様々な取組を行っています。
〔後継者育成事業〕
小原和紙工芸の後継者育成のため、小原和紙の歴史、技術などを学ぶ研修や小原和紙工芸会員による技術指導、公募美術展への出展などを行っています。
〔和紙原料の地産化〕
高齢化や後継者不足により、和紙原料の生産量は減っています。小原和紙のふるさとでは、耕作放棄地を利用してコウゾ栽培などに取り組み、地産化を目指しています。
日常生活に取り入れる
魅力あふれる小原和紙。こんなにも素敵なものがせっかく身近にあるのなら、自らの生活に取り入れてみませんか。ここでは、誰でも手軽に和紙の魅力を感じられる方法をご紹介します。
切って貼って飾るだけ 世界に1つのアートに

多彩な色味が味わえるのも魅力の1つ。その美しさを最も手軽に楽しむ方法は、そのまま飾って、見て楽しむこと。お金をかけずとも、普通の紙にはない和紙の質感や優しい色合いを日常的に楽しめて、おすすめです。

水をつけて手で引き伸ばすと、風合いを残し
ながら裁断できます

折って、貼り合わせて オリジナルの封筒に

好きな形にして貼って お気に入りのマグネットに

他にもたくさん 和紙の色々な使い方
「プレゼントを和紙で包んだり、メッセージを和紙に書いて渡したり。柔らかい触感やほのかに滲んだ文字とともに、思いがやさしく伝わります。百円均一などにある缶バッジ作成キットに使うのもおすすめ。ちょっとした工夫やアイデア次第で使い道は広がりますよ。」(小原和紙のふるさと スタッフ 齊藤 順子さん)
小原和紙のふるさと
和紙や小物類が購入できます。
和紙作り体験なども。
是非お越しください。
開館時間:午前9時~午後5時(体験受付は午後4時まで)
休館日:祝日を除く月曜日、年末年始
電話番号:0565-65-2151
(紙漉き体験の予約は電話番号:0565-65-2953)
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問合せ
小原和紙のふるさと
〒470-0562
愛知県豊田市永太郎町洞216-1(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)![]()
電話番号:0565-65-2151