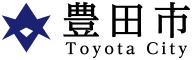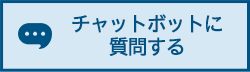国民年金保険料の免除等の申請
「法定免除」「免除・納付猶予」「学生納付特例」「産前産後免除」の制度があります。
法定免除
日本人が生活保護法による生活扶助を受けているときや、障害年金の1級・2級を受給しているときは、保険料が全額免除になります。国民年金被保険者関係届出書を提出してください。
免除・納付猶予
国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度があります。この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害を負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。
免除(全額免除・一部免除)申請
本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合や失業等の理由がある場合、申請して承認されると保険料が全額または一部免除となります。(一部免除の場合、減額された保険料を納付しないと一部免除が無効となり、未納期間となりますので、必ず減額された保険料を納付してください。)
納付猶予申請
50歳未満の人で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。
(備考)全額免除(納付猶予)となる所得の目安
{(扶養親族の数+1)×35万円}+32万円
(備考)免除・納付猶予の申請は、原則として毎年度必要です(免除等の1年度=7月~翌年6月)(継続申請の希望が承認された場合を除く。)。
(備考)過去期間は2年1か月前まで申請できますが、申請が遅れると障害年金が受け取れないなどの不利益が生じる場合がありますので、すみやかに申請してください。なお、7月初旬は窓口が大変混雑しますので、マイナポータルからの電子申請や、7月中下旬の窓口申請をお勧めします。
学生納付特例
学生納付特例制度は、学生の方が、申請により保険料の納付が猶予される制度です。この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害を負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。
(対象となる方)
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校等に在学する学生等で、申請年度の前年の所得が基準以下の方または失業等の理由がある方です。
(備考)所得の目安 128万円+{(扶養親族の数)×38万円}で計算した額以下
(備考)申請は、原則として毎年度必要です(免除等の1年度=4月~翌年3月)。
(備考)過去期間は2年1か月前まで申請できますが、申請が遅れると障害年金が受け取れないなどの不利益が生じる場合がありますので、すみやかに申請してください。なお、4月初旬は窓口が大変混雑しますので、マイナポータルからの電子申請や、4月中下旬の窓口申請、次年度以降については年金機構から送付されるはがきによる申請をお勧めします。
免除・納付猶予、学生納付特例の留意事項
退職特例制度
退職(失業等)により納付が困難な方は、特例免除を申請することができます。退職(失業等)された方の前年の所得を0円として審査されます。
(対象となる方)
申請者本人、世帯主または配偶者のいずれかが退職(失業等)された方
(保険料の納付が免除される期間)
失業等のあった月の前月から翌々年6月まで
(必要書類)
失業した事実が確認できる証明書類の写し(雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書 など離職日のわかる公共機関が発行した証明書)
免除・納付猶予された期間について
免除された期間があると、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る年金額がすくなくなります。
10年以内であれば、後から納めること(追納)ができます。追納すると、保険料を全額納付したときと同じになります。追納を行う場合は、お申し込みが必要です。詳しくは、お近くの年金事務所にご相談ください。
産前産後免除
産前産後期間の届出をすると国民年金保険料が免除されます。
産前産後期間の免除制度は他の免除制度とは異なり、保険料免除された期間も保険料を納付したものとして年金の受給額に反映されます。
(対象となる方・受付期間)
- 平成31年2月1日以降に出産された第1号被保険者の方
(妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産を含む)。) - 出産予定日の6か月前から届出ができます。(出産前の届出には母子健康手帳などの出産予定日が確認できるページのコピーを添付してください。)
(免除される期間)
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間、多胎妊娠の場合は出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から最大6か月間です。
- 産前産後期間の保険料を前納している場合、全額還付(返金)されます。
- 産前産後期間は付加保険料が納付できます。
届出
届出に必要なもの
- 窓口に来る人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証など)
- 被保険者(申請者)の個人番号もしくは基礎年金番号がわかるもの(マイナンバーカード、年金手帳など)(備考)窓口に来る人と異なる場合は委任状が必要な場合があります。
- 届出事由が証明できるもの
届出場所
お近くの年金事務所、国保年金課(南庁舎1階)、全ての支所・出張所(注釈)
市役所受付時間:午前8時30分~午後5時15分 土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く
(注釈)過年度分の申請は、支所・出張所ではできません。
関連情報
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問合せ
市民部 国保年金課
業務内容:国民健康保険・国民年金に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)![]()
国民健康保険に関すること 電話番号:0565-34-6637
国民年金に関すること 電話番号:0565-34-6638 ファクス番号:0565-34-6007
お問合せは専用フォームをご利用ください。