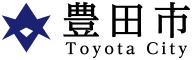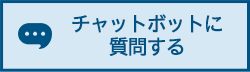後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は75歳以上(心身に一定以上の障がいがある場合は65歳以上も含む)を対象とする医療制度です。
後期高齢者医療制度とは、高齢化が進み、高齢者の医療費が増え続ける状況で、家族や社会のために長年尽くされた高齢者の方々が安心して医療を受け続けられるように、老人保健制度に代わって2008年4月から開始された制度です。
後期高齢者医療制度の医療に係る費用のうち、医療機関で支払う窓口負担を除いた部分について公費で約5割を負担、現役世代の保険料で約4割を負担し、残り約1割を被保険者が負担します。(備考)現役並みの所得のある方については、公費負担はありません。
愛知県の全市町村が加入する「愛知県後期高齢者医療広域連合」が後期高齢者医療制度を運営する主体(保険者)となり、保険料の決定、医療の給付、資格確認書等の発行などを行います。
市役所では保険料の徴収、資格確認書等等の引き渡し、各種申請や届出の受付などを担当します。
後期高齢者医療資格確認書
75歳に到達される方には、誕生日までに後期高齢者医療資格確認書が送付されます。この場合は交付のための申請は必要ありません。
愛知県外から転入した場合と、65歳以上75歳未満で一定の障がいがある方で後期高齢者医療制度に加入の申請をした場合は、資格確認書を交付します。
(備考)令和6年12月2日以降に後期高齢者医療制度の被保険者となる方については、令和8年7月末までの間における暫定的な運用として、申請によらず資格確認書を交付します。
転入又は加入申請に必要なもの
- 前住所地より発行された負担区分等証明書(愛知県外からの転入者のみ)
- 身体障がい者手帳など、障がいの程度を証明する書類(65歳以上75歳未満の場合のみ)
- 個人番号(マイナンバー)の確認ができるもの(個人番号カード、通知カード)
- 窓口に申請に来る方の本人確認ができるもの(運転免許証、資格確認書など)
(注意)本人及び世帯主以外の方が代理で手続きする場合、「委任状」または被保険者本人の印鑑が必要になります。
資格開始日
- 75歳の誕生日当日
- 65歳以上75歳未満で一定の障がい(注釈)と認定を受けた当日
(注意1)後期高齢者医療に該当された時点で、それまで加入していた健康保険の資格は喪失となり、それまでの健康保険資格確認書や高齢者医療受給者証は使えなくなります。
被保険者本人が後期高齢者医療に該当した場合、その被扶養者も同様に資格喪失となりますので、他の健康保険の被保険者又は被扶養者となるか、国民健康保険に加入していただく必要があります。
(注意2)65歳以上75歳未満で一定の障がいがある方については、申し出によって後期高齢者医療の資格を辞退することができます。
その場合は国民健康保険や被用者保険に加入して医療を受けることになり、心身障がい者医療助成や福祉給付金による医療助成などを受けることはできません。
(注釈)「一定の障がい」とは
- 身体障がい者手帳 1級~3級
- 身体障がい者手帳 4級(音声、言語、下肢1・3・4号)
- 療育(愛護)手帳 A判定(1度・2度)
- 精神障がい者保健福祉手帳 1級・2級
申請場所
福祉医療課(市役所東庁舎1階)、旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所
一部負担金
毎年8月、当該年度の課税所得(=市町村民税の課税標準額)と収入額を基に医療費の一部負担金の割合を見直します。なお、一部負担割合には1割、2割及び3割があります。
3割負担及び2割負担の基準は以下のとおりです。
負担割合 3割(区分:現役並み所得I~III)
対象者:市町村民税課税所得145万円以上の被保険者がいる世帯の被保険者
(備考)世帯に昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる場合、上記の基準に加え、その属する世帯の被保険者全員の旧ただし書所得(所得金額から基礎控除額を控除した金額)の合計額が210万円を超える場合
基準収入額適用申請
前年(前年1月から12月)の収入の合計額が以下の場合は、負担割合を「2割」または「1割」に変更できます。
- 世帯に後期高齢者医療被保険者が1人の場合:収入額が383万円未満
- 世帯に後期高齢者医療被保険者が2人以上の場合:収入額の合計が520万円未満
- 世帯に後期高齢者医療被保険者が1人で、その収入額が383万円以上あって、かつ同じ
世帯の70歳から74歳の方との収入額の合計額が520万円未満
(注意)判定における「収入」は必要経費等を差し引く前の金額です。所得が0円またはマイナスになる場合でも収入金額を合算します。
また、遺族年金などの市町村民税の課税対象とならない収入は、計算から除かれます。
調整控除
前年(療養を受ける期間が1~7月は前々年)12月31日時点で同一世帯に合計所得38万円以下の19歳未満の方がいる世帯の世帯主であった後期高齢者医療制度の被保険者については、市町村民税課税所得から以下の金額の合計を控除した金額で判定します。申請は不要です。
- 市町村民税課税所得から控除する金額
同一世帯の16歳未満の方の人数×33万円
同一世帯の16歳以上19歳未満の方の人数×12万円
負担割合 2割(区分:一般II)(備考)令和4年10月1日から新設
対象者:市町村民税非課税世帯以外の世帯であって、次の(1)及び(2)の両方に該当する世帯の被保険者(現役並み所得は除く)
(1)市町村民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる世帯
(2)被保険者が2人以上いる世帯の場合、世帯に属する被保険者の年金収入及びその他の合計所得金額が320万円以上(単身世帯の場合は200万円以上)
(備考)なお、市町村民税課税所得の判定には調整控除も適用されます。
一部負担金の特例(特定疾病療養受療証)
助成内容
以下の病気の治療は、ひと月の医療費の自己負担限度額が1つの医療機関につき10,000円に軽減されます。該当する方は、申請により「特定疾病療養受療証」が交付されます。
対象となる病気
- 人工透析を実施する慢性腎不全
- 血友病
- 血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症
申請に必要なもの
- 上記の疾病にかかっていることを明らかにする医師の意見書、または後期高齢者医療加入前の健康保険で発行された特定疾病療養受療証
(医師の意見書書式は福祉部福祉医療課、旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所にあります。また、ホームページからダウンロードができます。)
- 後期高齢者医療資格確認書等
- 個人番号(マイナンバー)の確認ができるもの(個人番号カード、通知カード)
- 窓口に申請に来る方の本人確認ができるもの(運転免許証、資格確認書など)
(注意)本人以外の方が代理で手続きする場合、「委任状」または被保険者本人の印鑑が必要になります。
申請場所
福祉医療課(市役所東庁舎1階)、旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所
任意記載事項併記申請(自己負担区分の記載など)
助成内容
申請により、自己負担区分(限度額適用区分)の情報など任意記載事項を資格確認書に記載することができます。
記載により、ひと月の医療機関・保険薬局等の窓口での支払い(自己負担限度額)と、入院時の食事代・居住費の標準負担額が下表のとおりに下がります。
【任意記載事項】
- 限度額適用区分と発行期日
- 長期入院該当日
- 特定疾病区分(A:人工透析、B:血友病、C:HIVの記号表示)と発行期日
(備考)適用区分について、詳しくは、以下のリンク先「適用区分について」をご参照ください。
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療資格確認書等
- 入院日数が確認できる領収書(区分IIで長期該当を申請する場合)
- 個人番号(マイナンバー)の確認ができるもの(個人番号カード、通知カード)
- 窓口に申請に来る方の本人確認ができるもの(運転免許証、資格確認書など)
(注意)本人以外の方が代理で手続きする場合、「委任状」または被保険者本人の印鑑が必要になります。
申請場所
福祉医療課(市役所東庁舎1階)、全ての支所・出張所
関連情報
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問合せ
福祉部 福祉医療課
業務内容:障がい者・子どもなどの医療費助成などに関すること
後期高齢者医療に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)![]()
医療費助成に関すること 電話番号:0565-34-6743
後期高齢者医療に関すること 電話番号:0565-34-6959 ファクス番号:0565-34-6732
お問合せは専用フォームをご利用ください。