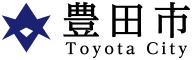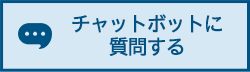特集 美しい、小原の和紙。 その2
小原和紙を知る
1 歴史
小原和紙のはじまりは、室町時代にまで遡ると言われています。
昭和初期までは、三河森下紙という番傘に用いる紙を生産していましたが、その後生活様式の変化などに伴い、需要は減少していきました。
そのような中、工芸家の藤井達吉が小原和紙の質の良さに着目し、小原の紙漉きたちに草木や土を使って和紙に色を付けることを指導しました。
さらに、染色した和紙原料を漉き込んで絵を描くことを考案し、藤井に師事した山内一生氏らによって小原和紙工芸として発展していきました。
現在は、額絵、屏風などのほか、現代の生活にも溶け込むランプシェードや壁紙などが制作されています。
2 伝統的な工法
原料の処理
12月から1月にかけて、和紙の原料となる「コウゾ」を刈り取ります。
大きな釜で蒸したら、温かいうちに樹皮を剝ぎ取り、付着している黒皮をそぎ落として白皮にします。
原料の加工
白皮を柔らかくなるまでアルカリ液で煮ます。
水で洗ってアク抜きをし、白皮のキズやゴミを丹念に取り除いたら、繊維が綿のように細かくなるまで叩きます。
紙漉き
舟(水槽)の中で繊維と水、粘液を混ぜます。
簀桁という専用の道具を前後左右に揺らし、和紙を漉きます。
漉いた和紙を重ね、水を絞り天日干しで乾燥させたら和紙の完成です。

3 継承に向けた取組
小原和紙のふるさとでは、小原和紙を後世へ伝えることを目的に、様々な取組を行っています。
後継者育成事業
小原和紙工芸の後継者育成のため、小原和紙の歴史、技術などを学ぶ研修や小原和紙工芸会員による技術指導、公募美術展への出展などを行っています。

和紙原料の地産化
高齢化や後継者不足により、和紙原料の生産量は減っています。
小原和紙のふるさとでは、耕作放棄地を利用してコウゾ栽培などに取り組み、地産化を目指しています。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問合せ
豊田市役所
〒471-8501 豊田市西町3丁目60番地
電話番号:0565-31-1212 ファクス番号:0565-33-2221