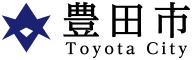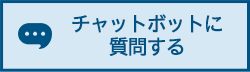施政方針
施政方針とは、市長の市政運営に対する考え方や政策・施策、予算について述べたものです。
一番下のPDFファイルからもダウンロードして見ることもできます。
令和7年度
前文
令和7年3月市議会定例会の開会に当たり、令和7年度の施政方針を申し上げます。
本市は、平成29年度以後の8年間、「第8次総合計画」に基づき、まちづくりを進めてまいりました。この「第8次総合計画」では、団塊の世代が後期高齢者となる「2025年問題」を意識し、超高齢社会に適応するための体制を整え、特に在宅医療に必要な仕組みを構築するとともに、豊田地域医療センターの再整備を行い、在宅医療を支える専門職の育成や地域リハビリテーションの拠点としての充実を図るなど、住み慣れた地域で安心して穏やかに暮らすことができるまちを目指して取組を進めてまいりました。
また、令和7年4月1日には近隣6町村との合併から20年を迎えることとなります。これまでの20年では、都市内分権による地域課題の解決を図るとともに、都市と山村の共生に向け、交流を通じた関係人口の創出など新たなつながりを生み出すまちづくりを進めてまいりました。
こうした本市のまちづくりに対しては、各種ランキングにおいて高い評価を得ております。例えば一般財団法人日本総合研究所による「全47都道府県幸福度ランキング」では、平成28年版の調査で中核市総合1位を獲得して以後、令和6年版の調査まで5回連続、期間にして10年間、中核市総合1位を継続しています。また、日本経済新聞社が編集・発行する「日経グローカル」令和6年度の全国市区「SDGs先進度調査」で1位を獲得するなど、これまで市民、地域、企業と共働で進めてきたまちづくりが、全国で高く評価されています。
このように高い評価を得たことは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大など、市民の暮らしを一変させる出来事を経験しながらも、本市のミライのフツーを目指すまちづくりが着実に進んでいることを示していると認識しています。
また、本市のまちづくりの成果については、令和7年10月に日本では初となる「2025国際首長フォーラム」を本市で開催し、SDGs達成に向けた取組とともに、世界各国の都市の代表者に発信してまいります。
こうした中、令和7年度から「第9次総合計画」に基づく、新しいまちづくりを開始します。
「第8次総合計画」がスタートした当時の社会環境とは異なり、本市においても、人口減少社会が到来しています。くわえて、これまで以上に社会経済情勢の変化が激しく、将来の予測が困難な社会となっています。
そのため、これまで積み上げてきたまちづくりの成果をしっかりと礎にしつつ、時代の変化に適応するまちづくりを進め、本市の将来を担うこどもたちの明るいミライにつながるまちの実現に取り組んでまいります。
特に「つながり」を改めて大切にし、こどもから高齢者まで幅広い世代がつながりを通して多様な価値や可能性を創出するとともに、「チェンジ」と「チャレンジ」をキーワードに掲げ、変化を受け入れ、これまで以上に新しいことに挑戦できるまちづくりを目指してまいります。そして、多様な地域特性や「クルマのまち」としての魅力を積極的に発信し、市民のまちへの愛着を高め、本市で暮らし続けたいと思えるようなまちの実現に向け、取組を進めてまいります。
一方、昨年を振り返りますと、1月1日に「令和6年能登半島地震」が発生し、大きな被害をもたらしました。また、豪雨による被害は、各地で頻発しており、これらの災害は本市においても、いつ発生してもおかしくない状況といえます。くわえて、8月には「南海トラフ地震臨時情報」が初めて発表され、改めて巨大地震への警戒や備えを確認する機会となりました。
こうした近年の災害の教訓を踏まえ、市民の生命や暮らしを守る安全・安心なまちづくりを着実に進めてまいります。
これらのことを念頭に置き、令和7年度に取り組む施策及び当初予算について申し上げます。
政策・施策について
始めに、令和7年度の施策について申し上げます。
令和7年度からの5年間で特に注力する取組の方向性を示す「第9次総合計画 ミライ実現戦略2030」においては5つの取組目標を掲げ、人口減少社会においても持続可能な都市として、また若年層を始め、広く人々にとって魅力のある「選ばれるまち」となるため、市民ニーズを的確に捉えながら、まちの総合力を高めてまいります。
特に少子化対策が待ったなしの中で、希望する全ての人が結婚や妊娠、出産等をかなえられる社会の実現に向けた様々な取組を進めるとともに、本市の将来を担うこども起点のまちづくり、誰もがつながり合うまちづくり、人を支えるまちの基盤づくりの3つを注力する視点として取組を進めてまいります。また、こうした取組を推進するために、市役所の組織改編を行うとともに、部局の垣根を超えたプロジェクト体制を新たに設置して、総力を挙げて取り組んでまいります。
こどもが多様な生き方・暮らし方を選択できる
取組目標の1つ目は「こどもが多様な生き方・暮らし方を選択できる」です。
変化の激しい予測困難な社会の中で、本市の多様な資源を生かして新たな魅力や価値を創造し、こどもがミライに希望を持つことができるまちを目指して、以下の4点について取組を進めてまいります。
あわせて、教育施策の根本的な方針である「教育大綱」の見直しを行ってまいります。
1 地域資源を生かした多様な「遊び・学び・体験」の機会の充実に向けた取組
1点目は、地域資源を生かした多様な「遊び・学び・体験」の機会の充実に向けた取組です。
こどもたちが、地域の大人など多世代とのつながりの中で、文化、スポーツ、ものづくりなどに親しむ様々な機会を提供してまいります。特に中学校の部活動に替わる「とよた地域クラブ活動」については、こどもが安心して参加できるよう、令和8年度からの市内全地域への展開に向けて取組を進めてまいります。また、人生100年時代をいきいきと暮らせるよう、大人に対しては、地域での新たなチャレンジや活躍へとつなげる学び直しの機会を提供してまいります。
2 自ら考え判断する力を育む教育の推進に向けた取組
2点目は、自ら考え判断する力を育む教育の推進に向けた取組です。
地域資源を生かし、各小中学校の特色ある授業でふるさとの魅力をこどもたちに伝えられるよう、博物館のアクティブ・ラーニングツアー等と連携した取組や矢作川流域学習プログラムなどのメニューをより活用しやすくした「WE LOVE とよた教育プログラム」を実施してまいります。
また、児童生徒一人ひとりに応じた学習と、こども同士や地域の人々などと共に取り組む学習の充実のため、学習用タブレットの更新に向けた準備を計画的に進めていくほか、きめ細やかな教育を推進するため非常勤講師などを適切に配置してまいります。
さらには、新たな学びを進めるため、小中一貫教育など魅力ある教育環境や学校施設の更なる有効活用を検討してまいります。くわえて、安全・安心で快適な教育環境を整えるため、夏の暑さ対策として、令和7年夏までに市内全ての小中学校の体育館・武道場に空調設備を整備するほか、地域体育館への空調設備導入に向けた調査を実施してまいります。
3 まちの歴史・文化・芸術や自然等をミライにつなぐ取組
3点目は、まちの歴史・文化・芸術や自然等をミライにつなぐ取組です。
令和6年4月に開館した博物館においては、本市への興味や関心を高め、愛着を持って暮らすことができるまちを実現するために、「みんなでつくりつづける」をコンセプトとして、とよはくパートナーなど市民や団体と連携し、調査や展示活動を推進してまいります。
また、美術館開館30年を記念して、印象派の巨匠を紹介する「モネ 睡蓮のとき」展を開催するほか、市内施設・事業者との連携により、ミュージアムを生かしたまちのにぎわいづくりを進めてまいります。
さらに、下山地区の観光をアクティビティ中心に活性化していくため三河湖周遊道路の整備を進めるとともに、足助の町並みにおける重要文化財旧鈴木家住宅の保存整備及び部分公開、棒の手会館展示リニューアルの実施設計を行うなど、文化財等の資源を生かして、地域への愛着や誇りの醸成、まちづくりへの活用を進めてまいります。
4 「クルマのまち」の更なる魅力の向上に向けた取組
4点目は、「クルマのまち」の更なる魅力の向上に向けた取組です。
令和7年11月に、主催者として3年目となる世界ラリー選手権を開催してまいります。安全・安心で魅力ある大会運営を通じ、ラリーを生かして地域の価値を高め、産業振興、山村振興、交通安全等を進めながら、改めて「クルマのまち」の魅力を発信・創出するとともに、地域を挙げた「おもてなし」の取組を引き続き進め、にぎわいの創出を図ってまいります。
そのほか、先進技術を使った移動支援事業として、自動運転に関する実証事業などモビリティに関する取組を公民連携で進めてまいります。
なお、新設する「魅力創造部」に「(仮称)観光誘客推進課」及び「(仮称)シティプロモーション戦略課」を設け、スポーツツーリズムを含めた観光振興を一体的に推進するほか、「クルマ」を始めとした本市の魅力をより積極的・戦略的に発信してまいります。
誰もがつながり合いの中で安心して自分らしく暮らすことができる
取組目標の2つ目は「誰もがつながり合いの中で安心して自分らしく暮らすことができる」です。
誰もが希望どおり結婚し、希望する誰もがこどもを持ち、安心して子育てができる環境づくりを進め、広く人々に選ばれる魅力的なまちを目指してまいります。また、こどもから高齢者まで全ての人がつながり合いの中で安心して自分らしく暮らせるまちを目指して、以下の2点について取組を進めてまいります。
1 まち全体でこどもの成長を支える取組
1点目は、まち全体でこどもの成長を支える取組です。
本市は、日経クロスウーマンと日本経済新聞社が発表した「2024年版共働き子育てしやすい街ランキング」において、東海地方で1位を獲得しました。また、中部地方初のユニセフ日本型CFCI実践自治体に承認されており、こどもや子育て当事者への施策が充実していることは、本市の強みであると認識しています。こうした強みを生かすとともに、更に広く人々から選ばれ、魅力的なまちとなるため、新婚世帯向けに結婚生活の支援を行うほか、賃貸住宅へのリノベーションに関する支援を行うなど、結婚期を迎える若者や子育て世代を主な対象として総合的な施策を進めてまいります。
くわえて、若年層を対象にライフデザイン形成への支援を新たに実施し、若い世代が持つ結婚・出産・子育て等の段階に応じた悩みの解消や、切れ目ない支援の充実に取り組んでまいります。
また、「(仮称)こども相談課」と「(仮称)おやこ応援課」を新設し、こどもと若者に関する相談機能の集約・強化と母子保健の充実を図るとともに、配慮が必要なこどもには、重層的支援体制による多機関が連携した支援をしてまいります。
さらには、経済的負担を軽減するため、こども園等の第2子保育料を無償とするほか、高校生の遠距離バス通学者への支援を新たに実施してまいります。
そのほか、乳児保育のニーズに対応するため、令和7年度からトヨタこども園と平山こども園で新たに乳児の受入れを開始するほか、入園要件のない0歳~2歳児の一時保育事業を拡大するなど、更なる子育て支援の充実を図ってまいります。
2 地域や多世代でのつながりを充実するための取組
2点目は、地域や多世代でのつながりを充実するための取組です。
本市は、共働による地域づくりの更なる推進に向け、支所権限の強化を図るとともに、「地域づくり振興基金」を活用し、より機動的に事業を進めることで、地域特性を生かした取組を一層推進してまいります。
また、新設する「(仮称)総合山村室」を中心に、山村地域における持続可能な地域運営や集落機能の維持について検討を進めるとともに、都市と山村の共生をより一層推進してまいります。
くわえて、本市は、地域共生社会の実現を目指し、全国に先駆けた取組を数多く展開してきました。さらに、一人ひとりが「生きがいや自分らしさ」を大切にしながら暮らしていくため、身近な地域に限らない新たな「つながり」を、多様な団体・事業者と連携して創出するなど、孤独・孤立予防の取組を進めてまいります。
産業中枢都市として深化し続ける
取組目標の3つ目は「産業中枢都市として深化し続ける」です。
本市は今後も産業中枢都市として圏域をリードし続けていく考えです。このため、市内の産業が更に発展していくための様々なチャレンジを後押しするとともに、誰もが働きやすい環境をつくり、多様な働き方・生き方が実現できるまちを目指し、以下の3点について取組を進めてまいります。
1 ミライを支える産業の創出と育成に向けた取組
1点目は、ミライを支える産業の創出と育成に向けた取組です。
本市の充実した都市基盤を最大限に活用し、更なる産業の集積・強化を図り、将来にわたって都市活力を持続できる産業構造の確立を図ります。特に企業の立地ニーズに対応するための産業用地の整備を推進するとともに、成長が見込める企業の投資に対する奨励金制度を新たに創設し、本市における成長産業の誘致・育成と既存事業者の設備投資を支援してまいります。
また、ものづくり創造拠点SENTAN(センタン)を拠点に、スタートアップ企業等の成長を促進するプログラムを実施するほか、ものづくり人材の育成やイノベーション創出に向けた取組を実施してまいります。さらに、愛知県による日本最大級のオープンイノベーション拠点「STATION Ai(ステーションエーアイ)」との連携を深め、市内企業等の新たな事業展開を促進してまいります。
2 市内事業者の持続可能性の向上に向けた取組
2点目は、市内事業者の持続可能性の向上に向けた取組です。
ものづくり中小企業のDXの促進や商業者の事業拡大等に係る支援など、市内事業者の経営力強化に向けた取組を拡充してまいります。
また、農産物の価値を高め、農業者の所得向上につなげるため、6次産業化等による販路拡大や市内農産物のブランド化、地産地食を推進するほか、民間活力の導入も視野に入れた公設地方卸売市場の再整備等を進め、市民の食を守るとともに、農業者を支援してまいります。
そのほか、森づくり人材の確保・育成や、店舗の木質化促進による地域材の認知度向上と利活用を促進し、持続可能な森づくりを推進してまいります。
3 多様な人材の活躍と柔軟な働き方の実現に向けた取組
3点目は、多様な人材の活躍と柔軟な働き方の実現に向けた取組です。
高校生向けのジョブフェアの開催やショートタイムワークによる新たな就労マッチング機会の提供を図るほか、キャリア形成やスキルアップの支援など、女性、高齢者、障がい者、外国人等の多様な人材の活躍に向けた取組を拡充してまいります。
また、地域企業の雇用確保と地域における人材活躍の場を創出するため、「(仮称)産業人材活躍課」を新設し、企業等の関係者が一体となって「人的資本経営」を支援する機能を強化してまいります。
将来を展望した都市環境の形成を進める
取組目標の4つ目は、「将来を展望した都市環境の形成を進める」です。
広大な市域の中で、市民の暮らしの質や地域活力を将来にわたって維持・向上させていくために、人口が集中する都市部と集落が点在する山間部の地域特性を踏まえ、次の世代が「住みたい・住み続けたい」と感じられるまちの実現を目指してまいります。
また、「令和6年能登半島地震」や頻発化・激甚化する豪雨等の自然災害を教訓に災害に強いまちを目指し、以下の2点について取組を進めてまいります。
1 次代につなぐ快適な都市環境の実現に向けた取組
1点目は、次代につなぐ快適な都市環境の実現に向けた取組です。
市内に26駅を有する鉄道の強みを最大限に生かした「えきちか居住」を促進するため、利便性の高い市街地形成に向けた土地利用計画制度の見直しを検討するなど、総合的な定住施策を進めてまいります。
また、人口が減少する中、点在し、老朽化が進行している公共施設の最適化により、暮らしに必要なサービスを拠点へ集積することで、暮らし機能の向上に取り組んでまいります。くわえて、山村地域においては、空き家・空き地情報バンクの運用や居住促進地区への住み替え等の支援を進めるなど、地域の暮らしの質の確保に取り組んでまいります。
さらに、本市の顔となる中心市街地の活性化を目指し、豊田市駅東口駅前広場等を整備するとともに、中央公園第二期先行整備区域については、令和8年度の開設を目指し、引き続き整備を進めてまいります。あわせて、もう一つの総合公園である毘森公園については、広く市民が利用する魅力にあふれた公園となるよう検討を進めてまいります。
くわえて、引き続き、豊田南・北バイパスや高橋細谷線、豊田刈谷線等の幹線道路の整備を図るとともに、令和7年度末の高架切替に向けて名鉄三河線若林駅付近の鉄道高架化事業を推進してまいります。そのほか、基幹交通ネットワークの維持と住民共助による生活交通の拡充に取り組んでまいります。
2 安全に暮らすことができる災害に強いまちに向けた取組
2点目は、安全に暮らすことができる災害に強いまちに向けた取組です。
「令和6年能登半島地震」に係る検証を踏まえ、備蓄物資の見直しを進めるとともに、災害時の医療救護や被災者の健康管理、特に災害関連死の防止に向けた取組を強化してまいります。くわえて、地域防災力の向上を図るため、消防団や自主防災組織の機能の充実や体制づくりを支援するとともに、個人や家族の防災行動計画である「マイ・タイムライン」の更なる普及促進を図るなど、自助・共助・公助による防災対策に取り組んでまいります。
また、近年の気候変動に伴い頻発化・激甚化する豪雨災害から市民の暮らしの安全・安心を守るため、国、県と連携し流域治水対策を推進しつつ、国の矢作川鵜の首地区狭さく部開削工事の早期着手に向けた支援を進めてまいります。このほか、上下水道施設については、「新水道耐震化プラン」及び「下水道総合地震対策計画」に加えて、「令和6年能登半島地震」を教訓とした国の新たな耐震指針に基づき、上下水道一体となった取組を推進してまいります。
くわえて、森林の持つ土砂災害防止機能や水源かん養機能等の公益的機能が最大限発揮されるよう人工林の間伐を促進するとともに、農地の持つ多面的機能を維持するための活動を支援するなど自然環境の適正な保全にも着実に取り組んでまいります。
脱炭素社会の実現に挑戦する
取組目標の5つ目は、「脱炭素社会の実現に挑戦する」です。
脱炭素社会の実現に向けて、市民・事業者・行政を含めた「オールとよた」で環境配慮行動に取り組むまちを目指してまいります。また、新たなエネルギーや技術の利活用に挑戦するまちを目指して、以下の2点について取組を進めてまいります。
1 市民・事業者・行政による脱炭素社会の実現に向けた取組
1点目は、市民・事業者・行政による脱炭素社会の実現に向けた取組です。
暮らしの中で一人ひとりが楽しみながら脱炭素行動を選択できるライフスタイルの定着を目指し、引き続き「とよた・ゼロカーボンアクション」を推進するとともに、フードドライブ活動の支援による食品ロスの削減や粗大ごみ等のリユースといった3R活動を進めてまいります。
また、市民を対象に、環境性能に優れたスマートハウスや、住宅で1年間に使用されるエネルギーの消費量の収支がおおむねゼロとなる「ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)」等に対する支援と蓄電池設置に対する支援を強化してまいります。
くわえて、事業者に対し、再生可能エネルギー設備の導入を引き続き促すとともに、市民・事業者へ次世代自動車の導入と太陽光発電設備の一体的な普及を促進してまいります。そのほか、公共施設の太陽光発電設備の導入や照明のLED化を進めてまいります。
2 新たなエネルギーや技術の利活用に向けた取組
2点目は、新たなエネルギーや技術の利活用に向けた取組です。
2050年のカーボンニュートラルの実現に向けて、水素に代表される新たなエネルギーの利活用を進めてまいります。特に令和7年3月に策定する「水素社会構築戦略」に基づき、「つくる」、「はこぶ」、「つかう」の3つの視点から、公民連携による豊田市版水素サプライチェーンを構築してまいります。その先駆けとして、令和7年度は、市内事業者のFCトラックと水素利用設備の導入を支援するとともに、水素活用に向けた市民や事業者に対するプロモーションを実施してまいります。
以上、「ミライ実現戦略2030」の5つの取組目標に資する施策を、総力を挙げて推進してまいります。また、引き続き、誰もが住み慣れた地域で安心して健やかに暮らせる地域共生社会の実現に向けて、市民の健康と福祉を支えるほか、行政手続の簡素化など、デジタルの活用を図りながら、市民の利便性向上につながる取組についても着実に進めてまいります。
当初予算
以上の取組を踏まえ、令和7年度の当初予算を編成してまいりました。
令和7年度当初予算は、社会環境の変化に的確に対応し、将来を見据えたまちづくりに挑戦するため「ミライ実現戦略2030」を推進する取組に重点的に配分してまいります。また、市民生活の「安全・安心」を確保する取組を着実に推進することを基本的な考え方として編成し、一般会計の総額は、2,197億円、対前年度243億円、12.4パーセントの増といたしました。
歳入では、法人市民税の減収などにより市税は1,246億円、対前年度9億円の減を見込み、基金繰入金は137億円、市債は40億円といたしました。
歳出では、普通建設事業費を451億円、維持補修費と合わせ492億円とし、引き続き計画的にまちづくりへの投資や公共施設等の適正な管理を進めてまいります。
今後の財政運営については、社会環境の変化のスピードが速く、先行きの見通しが難しい中、社会保障費や公共施設の維持管理と更新に係る経費の増加に加えて、物価上昇の影響などにより、厳しい状況が続くと見込まれます。市債と基金を効果的に活用しながら、国県補助金など歳入の積極的な確保に取り組み、限られた財源を効果的かつ効率的に市民サービスの充実として還元できるよう、事業・事務の最適化を図り、「将来に向けたまちづくりの推進」と「健全財政の維持」の両立を図ってまいります。
以上、令和7年度の施策及び当初予算につきまして、基本的な考えを申し上げました。何とぞ、皆様の御理解、御協力を賜りますよう、お願い申し上げます。
添付ファイル
PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問合せ
市長公室 秘書課
業務内容:式典、市表彰、危機管理などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎5階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)![]()
電話番号:0565-31-1212 ファクス番号:0565-33-7155
お問合せは専用フォームをご利用ください。