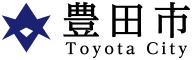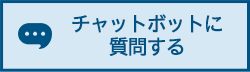特集 あなたの家でも起こるかも・・・家庭での食中毒対策
特集
あなたの家でも起こるかも・・・
家庭での食中毒対策

気温や湿度が上昇する夏場に、特に気をつけたいのは細菌による食中毒です。 家庭内でも、ちょっとした油断から食中毒は発生します。 自分自身はもちろん、家族みんなの健康のためにも、家庭で発生しやすい食中毒について知り、日頃から食中毒対策を心がけましょう。
命に関わることも!?症状が重い!
食品衛生のプロが選ぶ“警戒したい”食中毒トップ3
現場で日々食中毒の原因調査や患者の聞き取りなどを行っている市食品衛生監視員が、「特に気をつけたい」と思う食中毒上位3つを紹介します。
第1位 カンピロバクター
腹痛だけでなく、後遺症のリスクもある最も気をつけたい食中毒
激しい腹痛と下痢が続き、まれに手足の痛みやしびれなどの神経症状が続くギランバレー症候群になる恐れも。主に加熱不足の鶏肉が原因です。

市販の鶏肉の約7割にカンピロバクターが潜んでいる可能性が!
第2位 腸管出血性大腸菌(O157など)
家庭内感染にも注意!重症化の恐れがある、次に気をつけたい食中毒
激しい腹痛と血便が出るほどの下痢が続き、重症化すると腎不全になる恐れも。また感染力が強く、食事やトイレを介して家族間で感染する可能性があります。主に加熱不足の牛肉が原因です。
第3位 黄色ブドウ球菌
短時間で症状が現れる、実は身近で多い食中毒
食後数時間で突然の激しい嘔吐を引き起こします。人の手や体の菌が食べ物に付くことが原因です。

特に手に傷があるときは、ラップを使って対策!
家庭での食中毒に苦しまないために
家庭での食中毒を防ぐためには、細菌を「つけない」「増やさない」「やっつける」という三原則の徹底が大切です。次のポイントを意識してみましょう。
つけない
- こまめに手を洗う
調理や食事の前、トイレの後、生肉や魚介類を触ったときは、食中毒菌を広げないためにその都度手を洗うことが大切です。 - 調理器具は使い回さない
調理器具は使い回さず、肉や魚と野菜で分けて使用するのが望ましいです。また、下処理は野菜→肉や魚の順番に行うことで、菌が食材から食材へ広がるのを防ぐことができます。
増やさない
- 速やかに食べる
長時間の放置や作り置きを控え、すぐに食べるのがおすすめです。 - 低温で保存する
食中毒菌は10℃~60℃で増殖します。すぐに食べない場合は保存容器に小分けにして粗熱を取り、できるだけ早く冷蔵庫で保存することを心がけましょう。
やっつける
- 十分に加熱する
食中毒菌は、75℃で1分以上の加熱により死滅します。中まで火が通りにくい料理は、料理用の温度計を使うこともおすすめです。電子レンジでの加熱はムラができやすいため、かき混ぜながら全体が温まっているかを確認すると安心です。
食中毒が発生しやすい日をお知らせします
6月末から9月までの間、愛知県では食中毒が発生しやすい気象条件の日に食中毒警報が発令されます。市においても、発令時には緊急メールとよたや市公式SNSなどで情報発信を行いますので、是非ご確認ください。