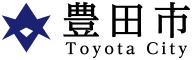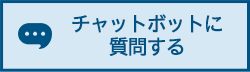奈良 平安時代・鎌倉 室町時代・戦国時代・江戸時代(とよたの起源)
豊田市の起源をご紹介します。
奈良・平安時代

6世紀に伝来した仏教は次第に広まり、奈良時代には市内にも舞木廃寺(舞木町)、伊保白鳳寺(保見町)などいくつかの寺が建立されました。

また、平安時代になると、豊田市域にも朝廷の支配のもとで10ほどの「郷(ごう)」が形成されました。現在の伊保、高橋、挙母(衣)、畝部、若林などはそうした郷の一部でした。こうした郷の印として、「伊保郷印」(市指定文化財)が現在に伝わっています。平安時代後期には、地方にいくつもの荘園が作られましたが、豊田市域では高橋荘、足助荘、碧海荘、重原荘などが知られています。
鎌倉・室町時代
1192年に成立した鎌倉幕府は、特に西三河地方に重臣を送って支配の強化に努めました。高橋荘地頭に任命された中条氏は、猿投神社とのつながりが深く、多くの宝物を寄進しています。金谷町にある衣城(金谷城)は、中条氏が拠点とした城であると考えられます。
このころには、既に矢作川の水運を利用した交易が行われ、市があったと考えられています。
戦国時代
戦国時代を迎えると、中条氏の勢力は衰え始め、この地方では松平氏(後の徳川氏)、鈴木氏、三宅氏などの土豪が互いに勢力を競い合うようになりました。
豊田市域は今川、織田、松平の3者の接点ということもあって絶えず戦いが繰り返されていました。市内長興寺に伝わる織田信長画像(国指定文化財)や、今川義元文書(市内永澤寺蔵 市指定文化財)から、かつての支配者を伺い知ることができます。
また、武将たちが戦いの拠点とした松平城、大給城、岩倉城、伊保西古城、広瀬城、寺部城などの城跡が今も残っています。
江戸時代

江戸時代の市域は、衣藩(後挙母藩)、伊保藩、刈谷藩、岡崎藩や旗本領、寺社領(猿投神社領・隣松寺領など)が入り乱れる地域でした。
衣藩は、1604(慶長9)年に三宅康貞が一万石の大名として封じられたことに始まります。その後、本多家、内藤家と領主が替わりました。
1749(寛延2)年に挙母藩主となった内藤家は、明治維新まで7代にわたりこの地を治めました。
この内藤家がニ万石となって、挙母城の築城が進められました。当初は桜城(桜町)、その後洪水により移動し、七州城(小坂本町)が居城となりました。挙母の城下町は、はじめ7町でしたが、次第に8町へと発展しました。現在も続けられる挙母まつりの山車に、かつての城下町の繁栄を伺い知ることができます。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問合せ
市長公室 広報課
業務内容:広報とよた、報道対応、CATV市政番組、ラジオ市政番組、市政記録映像、市ホームページ管理運営などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)![]()
電話番号:0565-34-6604 ファクス番号:0565-34-1528
お問合せは専用フォームをご利用ください。